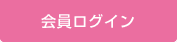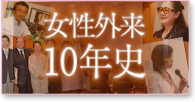2022.08.12
正解の無い難問『減量』
今回は、桜医院 柴田美奈子院長からの投稿です。
皆様こんにちわ。猛暑と新型コロナ感染爆発のこの夏を、無事に乗り越えられましたでしょうか?
さて、このコラムをお読みのそこの貴女。貴女はダイエットに真剣に取り組んだことはありますか?何回くらい?そしてそれはいつも成功していますか?
私は小学生の頃から40年以上に渡って、ダイエットに真剣に、そして何度も、色々な方法で取り組んできたプロのダイエッターです。「プロの」とつけるのは、自分自身の事だけでなく、多くの患者さん達の減量指導にも関わってきたからです。
ここでまずは、言葉の訂正。「ダイエット=減量努力」と勘違いされている方が日本人には多く見られますが、ダイエットという言葉は本来、食事療法のことで、減量は食事だけでなく、運動や生活習慣のあらゆるところの見直しが必要なので、正しい言葉の使い方をするため、ここからはダイエットという言い方は封印して、正しく「減量もしくは減量努力」という言い方に統一していきます。
さて、その減量に関するバイブルともいうべき書籍が2019年に刊行されたのはご存知でしょうか?
カナダ人の透析医であるドクター ジェイソン・ファンがお書きになった「The Obesity Code」(邦題 世界最新の太らないカラダ)です。500ページほどのその本には、世界中の減量努力に関する歴史と、最新の減量に関する医学的理論、社会学的・経済学的な肥満と減量との考察などが書かれています。日本語訳版が発売された時には、私もすぐさま書店で何冊も買い込み、自宅や職場のあちこちに置いて、空き時間を見つけては読み進めたものです。特別に新しい知識が書かれているわけではなく、これまでの当たり前の「栄養医科学」の論理ではいかに現実的に「減量は難しいもの」であるかが書かれています。そして透析医として長年、糖尿病の患者さんをたくさん診てこられたドクターファンは、インスリンの分泌回数をいかに減らすかが減量の鍵であると結論づけ、36時間の間欠的ファスティングの食事方法を最終章に提示しています。
「ナーンだ、最後は結局ファスティング(断食)なのね。。。」と、そこまで読み進んだ私は当時ちょっとガッカリしたのを記憶しています。なぜなら、インスリンの分泌は食品のGI値との関係が大きく、それまでもそれを踏まえた減量方法をいくつも見てきましたが、結局それだけでは説明のつかない症例もたくさん診ていること、またファスティング自体も、私が何度も取り組み、そして結果を出せなかった減量手段の一つだったからです。この本の内容もいつしか「この時代の減量の主流はこういうメソッドだったね」になるのかもしれないな。。。と感じています。
日本でも減量の歴史には色々な流行り廃りがありました。りんごやバナナなどの単品だけを食べるもの、栄養補助ドリンクを購入して1食置き換えにするもの、運動ならエアロビクスブームもありましたし、コアリズムなんてウエストをひねりまくるダンスが流行った時もありました。デトックス道場と名打ったホテルで、三泊四日人参ジュースだけを飲むソフト断食がおしゃれ女子の間で流行ったり、はたまた韓国の美魔女系の女優さんは一日6食に分けて少量ずつ食べるらしいと聞けば、今度はそちらに寄せてみたり。。。単なるブームだけにとどまらず、減量に関する医学的論理も、二転三転どころか、全く理屈がひっくり変える事も多々経験してきました。カロリー制限が主流だった私の子供時代から、「そんなのは古い考え、これからはお米と白糖とショートニングを食べないことだよ」に変わったのは20代の頃。当時はほとんどお米を食べず、コーヒー紅茶に入れるお砂糖を人工甘味料に全て切り換えていました。30代になると「女性も筋肉をつけて代謝を上げることで同じ体脂肪率でも見た目が全然違うのだ」という考えが主流に、女性用の筋トレジムが大ブームになり、私も筋トレ女子になり、「いつか正しい運動をしっかり指導できるクリニックを開設したい」と夢を持つようになります。
その陰で、GI値が低く自然で健康的な甘味料とされていたアガベシロップが、実は肝機能を悪くするというデーターが発表されたり、「運動運動と言っても基本はやっぱりカロリーバランスが第一」というカリスマ運動療法士の本がバカ売れしたり、それでいて毎月、1週間のソフト断食を繰り返している自分は全然痩せない。。。、また私が外来で診ている更年期の女性達は、他の年代の女性達に比べて特別に痩せづらく太りやすい。。。といった現実も突きつけられていきます。気づけば、既に40代後半になっていた私は、念願の「運動指導ができるクリニック」桜医院を開設しましたが、ちょうどその頃から、若い頃には感じなかった運動器の故障を、運動すればするほど、全身のあちこちに実感するようになっていました。私も更年期に突入したからです。東金病院で女性専用外来を担当し始めた頃は46kgだった私も、すっかり中年太りのおばさんになっていました。
さてさて、前置きがかなり長くなりました。
減量とはいかに難しく、そしてそのメカニズムはまだまだ医学的には未知の部分も多く、現在進行形、今も試行錯誤の日々であることをお伝えした上で、私が臨床医療の一環として、真剣に、自分そして患者さん達の減量に向き合っているその日々の格闘をお伝えしていきたいと思います。
後編に続く。。。。
後編の予告 5つのポイント
1) 減量で未来は変わる!
大きな病気を予防、国の医療費も大きく削減!!
2) 腸内環境。唯一わかっている医学的に太る体質・痩せる体質
3) 基本はやっぱり適量の食べ方。食物繊維にミネラル、PFCバランス
4) それでもやっぱり運動もしなくちゃいけない!筋肉や血液データは裏切らないし、誤魔化せない。
5) 痩せの大食いは実際にいる、でも貴女には貴女にできることがある。諦めない、挫けない!!
桜医院 院長 柴田美奈子