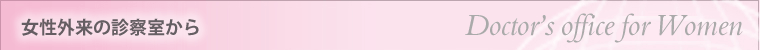
CFS=慢性疲労症候群。2015年4月22日(水曜日)、衆議院第一議員会館、地下1階大会議室にて、平成26年度厚生労働省委託研究「慢性疲労症候群患者の日常生活困難度調査事業」の報告会が行われました。
プログラムは下記のとおりです。
12:00 開会 主催者挨拶と来賓からのご挨拶
12:15 実態調査の報告:遊道和雄 (聖マリアンナ医科大学教授)
13:05 患者自身の声 篠原三惠子 (NPO法人筋痛性脳脊髄炎の会理事長)
13:20 和温療法の話 天野惠子 (静風荘病院特別顧問)
13:50 閉会の挨拶
14:10 記者会見
調査報告の概要が、医療向け情報誌「集中」に掲載されましたので、引用して、ご紹介いたします。
慢性疲労症候群は激しい倦怠感に襲われ、生活が著しく損なわれるほどの強い疲労とともに、頭痛や微熱、筋肉痛などの症状と思考力・集中力低下などをもたらす疾患ですが、原因は不明で、明確な治療法はなく、患者の生活実態もほとんど把握できていませんでした。
今回の調査の主目的は、「日常生活の困難度を明らかにすること」と設定され、医療機関で診断された男女計251人(平均41.8歳)に聞き取り調査が行われました。男女比は、男性が22%、女性が78%。発症年齢は平均30歳ほどで、罹病期間は6~7年でした。
「筋痛性脳脊髄炎」(慢性疲労症候群)の患者は全国で24~38万人に上ると推測されていますが、今回の調査で、ほぼ3割が「日中の半分以上寝たきり」であることが明らかになりました。
重症度はバイオマーカーなどの数値がないため、パフォーマンスステータス(PS値)で分類しています。「月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要」という3以上が慢性疲労症候群と診断され、3から「週のうち数日は自宅での休息が必要」な5までが軽症、「週の半数は自宅休息が必要」である6と「通常の社会生活が不可能」な7を中等度、「日中の半分以上は就床している」8と「常に介助が必要で終日就床」な9を重症としています。その結果、軽症が31.5%、中等度が35.1%、重症が30.2%でした。「発症に関与したと考えられる要因」としては、複数回答で「感染症」76人(30.3%)、「発熱」68人(27.1%)などが多く、「思い当たらない」も51人(20.3%)いました。遊道センター長は「著しい消耗症状が起きていたことを確認した」と述べています。
「調査時の症状」としては、「肉体的精神的疲労」の88.8%を筆頭に、「回復に24時間以上かかり悪化傾向」、「広汎な筋肉痛」「集中力低下」などが多く挙げられていました。
「症状を悪化させる事がら」は、「無理をせざるを得ない」「気圧・季節の変化」「ストレス」が過半数を超えていました。
「痛みの症状」については、「強い」「眠れないほど強い」が合わせて75%に上り、頻度は37%が「常時」と答えています。遊道センター長は「頭痛、全身の筋肉・関節痛などの耐えられない痛みを常時感じていることが分かった。睡眠障害もあり、7割が睡眠導入剤を使っていた」とコメントしました。
「歩ける距離」でも顕著な数値が出ています。重症患者は「歩けない」が15.3%、「10m以内」が27.8%。全体でも18.9%が10m以内しか歩けませんでした。重症患者はトイレくらいにしか行けないということです。
就学・就労状況も調べられました。発症時に通学していた患者は61人(24.3%)で、小学生も9人いました。そして、発症後に通学を続けられたのは26人(42.6%)にとどまっていました。就労状況では全体の71.7%が働いていませんでした。
「困りごと」として挙がったのは、「症状が耐えがたい」「専門医がいない」「社会的孤立」の順でした。「行政に望むこと」では、「病気の研究」「病気の認知」「医療費助成」などが並びました。
遊道センター長は「患者さんは、専門医がいないこと、治療法が確定しないこと、病気への無理解や社会からの孤立を訴えている状況。行政にはサービスを受けやすくしてほしい」と述べました。
自身も寝たきりの患者である、NPO法人「筋痛性脳脊髄炎の会」(旧「慢性疲労症候群をともに考える会」)の篠原三惠子理事長は、「周囲の理解が得られずに無理をして悪化している人が多い。患者会の代表をしている私でさえ、患者さんとの交流は少ない。他の人はどうしているのだろうと心配になる。実態が社会に知られていないのが問題で、今回の調査で浮かび上がったことが正しい認識につながることを心から願っている」と訴えました。
大会議室には患者さんとその家族、国会議員(参議院議員、衆議院議員)、厚生労働省からの参加者、患者さんのサポーター、メディアの方など多くの方に参加していただき、記者のかたがたの関心は調査報告にあったようですが、患者さんとその家族、そしてサポーターのかたがたの関心は、和温療法にあったように思います。
和温療法がこの疾患の早い段階で、患者さんが利用でき、その費用負担が少なくなることを祈るばかりです。
Copyright © 2014 Japan NAHW Network. All Rights Reserved.