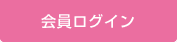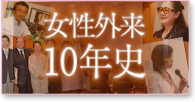2017.12.05
大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会に参加して
弘前大学 皮膚科学講座助教 皆川 智子先生の投稿です。
平成29年9月29日 大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会―よりよい男女共同参画を目指してーが日本医師会館大講堂で行われ、参加いたしました。
日本医師会女性医師バンクでは復職支援も行われていますが、登録された先生方の年齢別グラフがあり、これまでの出産育児などのライフイベントと考えられる30代に加え、介護が理由と考えられる50代が増えていることが紹介されました。
私の夫は一人息子なので、自分の両親とあわせて4人の介護が待ち受けており、今後困ったときには相談したいと思いました。
また広報活動紹介として、女性医師バンク利用者は主に子育て世代のため今後支援を必要とする若い世代に向けての情報発信ツールとしてFacebook(SNS)を活用していくことが報告されました。
Facebookの活用はコスト削減にもつながりますので、拝見し、いいね! をクリックしようと思いました。
さらに、都道府県医師会との取り組みとして、育児中の医師の学習機会の確保のため、医師会主催の講習会等への託児サービス併設促進と補助があげられていました。
青森県医師会でも研修会・講演会・講習会などへの託児施設の併設促進と費用の補助をされております。
働く医師が心身ともに健康でなければ、患者さんによい医療を提供するのは難しいため、みんなが笑顔で働けるよう一人でも多くの医学生が卒後青森県で活躍いただけたらと思いました。
次に、女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告についてですが、日本医師会で全病院(8475施設)に対して、病院・診療所に勤務する女性医師に調査票の配布を依頼し、有効回答数:10373枚を検討した結果が報告されました。
その中で個人的に気になった項目を以下に抜粋します。
①診療科別勤務形態
病理・検査科,外科,泌尿器科,救急科等では常勤の割合85%を超え、脳神経外科では93%となっていた一方、眼科・放射線科では81%未満,内科・耳鼻咽喉科・皮膚科では80%未満であった。
②子どもの緊急時の対応
本人が休暇をとるなどして対応した割合をみると、現在乳幼児子育て中の常勤者では47%,時短常勤者58%,非常勤者55%であるのに対し、子育て経験者では本人は32%にとどまり、親・親族が43%であった。
③緊急時の呼び出し
「呼び出しなし」「断るまたは他の医師に依頼する」をあわせ現在乳幼児子育て中の常勤者では47%,時短常勤者66%,非常勤者65%であるのに対し、子育て経験者では本人は28%にとどまった。子育て経験者のそのほかの内訳は「呼び出しなし」158名「断るまたは他の医師に依頼する」453名「連れていく」204名「夫が保育」804名「外部に預ける」129名「親等に預ける」410名「その他」56名であった。
以上の報告から、実際に勤務医として働き続けるのは、親元でないと難しいと感じながら帰路につきました。
実際に私も外来患者さんのことで急遽呼び出され,心臓血管外科医の夫は出張か手術中で、やむなく子連れでいったこともあります。
また、急遽のことで実家も不在で,児童センターからは最近不審者もいるので17:30以降はできればお迎えをといわれ、やむなくタクシーで大学病院に息子を連れ来てもらい、附属病院女性医師支援センター多目的室を利用したこともあります。
今回のアンケートからもわかりますが、自分自身が医師と家庭の両立が難しい状況では女性外来立ち上げは、なかなか難しそうだなと思う今日この頃です。
弘前大学 皮膚科学講座 皆川 智子