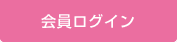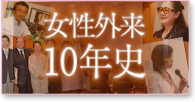2016.07.25
沢山の手で育てる、ということ。
私には1人の娘がいます。
私が産後体調を壊したこと、また、仕事と育児を両立させるため、娘の生後3ヶ月から保育園を利用していました。
その中でずっと支えられてきた哲学というべき言葉があります。
「沢山の手で育てられる幸せ」という言葉です。
障害児童に関わる、ある大学病院の看護士の方の言葉です。
重度の障害児童が生まれた場合、そのご両親だけで育てることは困難を極めます。
ご両親はもとより、親戚やご近所などにも障害児童の育児経験のある人がいないため、正確なアドバイスがもらえず、ご両親の専門的な障害の知識も薄いため、ともすると子どもに誤った接し方をしてしまい、親子双方疲弊する場合もあります。
決して育児を抱え込まず、専門家や経験のある人々大勢で育てられる環境の方が、むしろ十分にその子どもの能力を活かせる、親子ともハッピーである、というご意見です。
自らの娘の育児をする中で、このことは決して障害児という特殊な個性の子どもを育てるケースにおいてだけの話ではないことに気がつきました。
自治体には、保健士による保育相談サービスがありますが、2歳くらいのお子さんをつれて「近所の同じ年の子どものように言葉が進まない。うちの子は障害があるのでは・・・」という専業主婦のお母さんが最近はよくお見えになることがあるそうです。
色々お話を伺った上で保健士さんが行ったアドバイスは「お子さんを一時保育でもよいので、保育園に預けてみましょう。」ということでした。
お母さんは大変物静かな女性で、お父さんは忙しく毎日お子さんが寝てしまってからの帰宅。お子さんは人間同士の会話を耳にする機会が極めて少ない環境で過ごしている、という保健士さんの観察でした。
お母さんの比較している「同じ年の子どもたち」は、ご両親が共働きで保育園児童が多かったようです。保育園では歌ったり踊ったりのプログラムがあり、また預けられる子の年齢に幅があり、年上のよくしゃべるお子さんも毎日身近に複数います。
先生方も、沢山の子どもを見守る過程で注意・提案・指示など、自宅にいるお母さんよりは子どもたちと会話をします。
子どもの脳は五感で外部刺激を感じて、成長しています。
外部刺激が少ない環境で成長が遅いのは、当たり前なのですね。
反対に、その子の個性や可能性をできるだけ広げるためには、多様な人々との会話・接触・観察といった多様な外部刺激があったほうがよいことは言うまでもないでしょう。
そして、子どもが早い段階から多様な価値観で人生を生きられることは、自分とは異なる環境で育った人々と接しながら生きてゆく過程において心強い武器となるでしょう。
「沢山の手で育てられる幸せ」という言葉を私に教えて下さったあの看護士の方のことを時々思い出し、頭が下がる思いです。
㈱ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員
JADP上級心理カウンセラー 天野 馨南子